下痢が止まらない…もしかして「胆汁性下痢」?知っておきたい原因と治療法

川崎駅前大腸と胃の消化器内視鏡・肛門外科クリニック(通称:カワナイ)です。
久しぶりの消化器に関するブログになります。先日、患者様からご質問があり、詳しく調べたのでまとめてみました。
「長引く下痢に悩んでいるけれど、原因がはっきりしない…」 「普通の胃腸薬が効かない下痢が続いている…」というお悩みの方にお伝えしたい内容になります。
慢性の下痢は、日常生活に大きな影響を及ぼし、精神的なストレスも大きいものです。下痢の原因は様々です。
近年、過敏性腸症候群などの病気が定義され、様々な薬が出来てきました。その他にも、聞き慣れない「胆汁性下痢(たんじゅうせいげり)」と呼ばれるものがあります。
今回はこの胆汁性下痢について、その原因、症状、そして適切な診断と治療法について詳しく解説したいと思います。もし長引く下痢でお悩みでしたら、ぜひ最後までお読みいただき、川崎駅前大腸と胃の消化器内視鏡・肛門外科クリニック(通称:カワナイ)受診のきっかけにしてください。
1.下痢が胆汁と関係あるの?「胆汁性下痢」とは?
「胆汁」は、肝臓で作られ、脂肪の消化吸収を助ける働きを持つ消化液です。通常、胆汁は胆嚢に一時的に貯蔵され、食事が十二指腸に送られると分泌されます。その後、小腸で脂肪の消化吸収を助けた後、大部分が小腸の最後の部分(回腸末端)で再吸収され、肝臓に戻って再利用されます。
しかし、この胆汁の再吸収がうまくいかなかったり、胆汁の分泌量が過剰になったりすると、大腸に流れ込む胆汁の量が増え、下痢を引き起こすことがあります。これが「胆汁性下痢」です。
胆汁は、大腸の粘膜を刺激したり、大腸内の水分分泌を促したりする作用があるため、下痢の原因になります。
2.なぜ「胆汁性下痢」になるの?主な原因
胆汁性下痢の主な原因は、大きく分けて二つあります。
(1) 胆汁の再吸収がうまくいかない場合
- 胆嚢摘出後:最も一般的な原因の一つです。胆嚢は胆汁を貯蔵・濃縮する臓器であるため、摘出すると、食事とは関係なく胆汁が常に少量ずつ十二指腸へ流れ出てしまうことがあります。その結果、小腸での再吸収が追いつかず、大腸に流れ込む胆汁が増えて下痢を引き起こします。
- 小腸の病気や手術:胆汁が再吸収される場所である小腸の回腸末端に炎症がある場合(クローン病など)や、その部分を切除する手術を受けた場合(大腸がんの手術など)に、胆汁の再吸収が阻害されて起こります。
- 薬剤の影響:一部の薬剤(特にメトホルミンなど)が胆汁の代謝や再吸収に影響を与える可能性も指摘されています。
(2) 胆汁の分泌量が過剰な場合
- 原因不明(特発性):検査をしても小腸の病気や手術歴がなく、胆嚢も切除していないにもかかわらず、胆汁の分泌や代謝に異常が生じて下痢が続くケースです。これが最も多く、診断が難しい場合があります。
- 機能性消化管疾患:過敏性腸症候群(IBS)の下痢型の方の中には、胆汁酸の代謝異常が関与している可能性が指摘されています。こちらも診断は難しいです。
3.もしかして胆汁性下痢?主な症状と特徴
胆汁性下痢は、一般的な下痢と区別がつきにくい場合もありますが、以下のような特徴が見られることがあります。
- 水様性~泥状の下痢: 便が特に水っぽく、急に起こることが多いです。
- 排便回数が多い: 1日に何回もトイレに行くことがあります。
- 便の色: 胆汁の色(黄色~緑色)が薄く残っているため、便の色がやや黄色っぽい、または緑っぽいことがあります。ただし、これは常に明確に見られるわけではありません。
- 腹痛や腹部の不快感: 下痢に伴って、お腹がゴロゴロ鳴ったり、差し込むような腹痛を感じたりすることもあります。
- 急な便意(便意切迫): 突然強い便意を感じ、我慢しにくいことがあります。
特に、胆嚢を摘出した経験がある方で、このような下痢が続いている場合は、胆汁性下痢の可能性が高いと考えられます。
4.胆汁性下痢の診断と治療法
長引く下痢は、胆汁性下痢以外の病気が原因である可能性も十分にあります。自己判断せずに、まずは医療機関を受診し、適切な診断を受けることが重要です。
診断方法
川崎駅前大腸と胃の消化器内視鏡・肛門外科クリニックでは、まず問診で症状や既往歴(特に胆嚢摘出の有無、腸の病気など)を詳しくお伺いします。
- 便検査: 便中の胆汁酸濃度を調べる検査を行うことがあります。(ただし、この検査は限られた施設でしか行えない場合があります。当院でも施行できません)
- 血液検査: 炎症の有無や栄養状態などを確認します。腸炎などの病気が潜んでいないか
- 大腸内視鏡検査、胃内視鏡検査: 他の原因による下痢(炎症性腸疾患、大腸がん、感染症など)を除外するために、これらの検査を行うことがあります。特に、大腸内視鏡検査は、大腸の粘膜の状態を直接確認する上で非常に重要です。
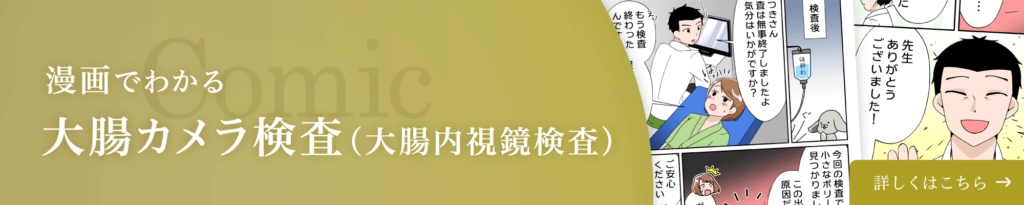
これらの検査で他の病気が除外され、症状や既往歴から胆汁性下痢が強く疑われる場合に診断に至ります。
治療法
胆汁性下痢と診断された場合、主に以下のような治療が行われます。
- 胆汁酸吸着剤: 胆汁酸を吸着し、大腸への刺激を抑える薬(例:コレスチラミン、コレスチミドなど)が処方されます。これにより、下痢の症状を劇的に改善できることがあります。
- 食事療法: 脂肪の摂取量を減らすことで、胆汁の分泌を抑え、症状の軽減を目指すことがあります。ただし、極端な食事制限は必要ない場合がほとんどです。
- 基礎疾患の治療: 小腸の炎症性疾患が原因の場合は、その疾患に対する治療を行います。
5.長引く下痢は放置しない!専門医にご相談を
胆汁性下痢は、適切な診断と治療を行うことで、症状を大きく改善できる可能性があります。しかし、単なる「お腹が弱い」と自己判断して放置してしまうと、症状が長引き、生活の質が低下するだけでなく、他の重篤な病気を見過ごしてしまうリスクもあります。
特に、便の色がいつもと違う、血が混じる、体重が減る、激しい腹痛があるといった症状がある場合は、すぐに医療機関を受診してください。
川崎駅前大腸と胃の消化器内視鏡・肛門外科クリニックでは、消化器病専門医が長引く下痢の原因を多角的に診断し、患者さん一人ひとりに合わせた最適な治療をご提案いたします。つらい下痢の症状でお悩みでしたら、お気軽にご相談ください。
【川崎駅前大腸と胃の消化器内視鏡・肛門外科クリニックへのご予約はこちらから】
【アクセス情報はこちら】
〒210-0006 神奈川県川崎市川崎区砂子2-4-17
【共に働く仲間(スタッフ)も募集しています。】https://www.kawasaki-naishikyo-recruit.com/
